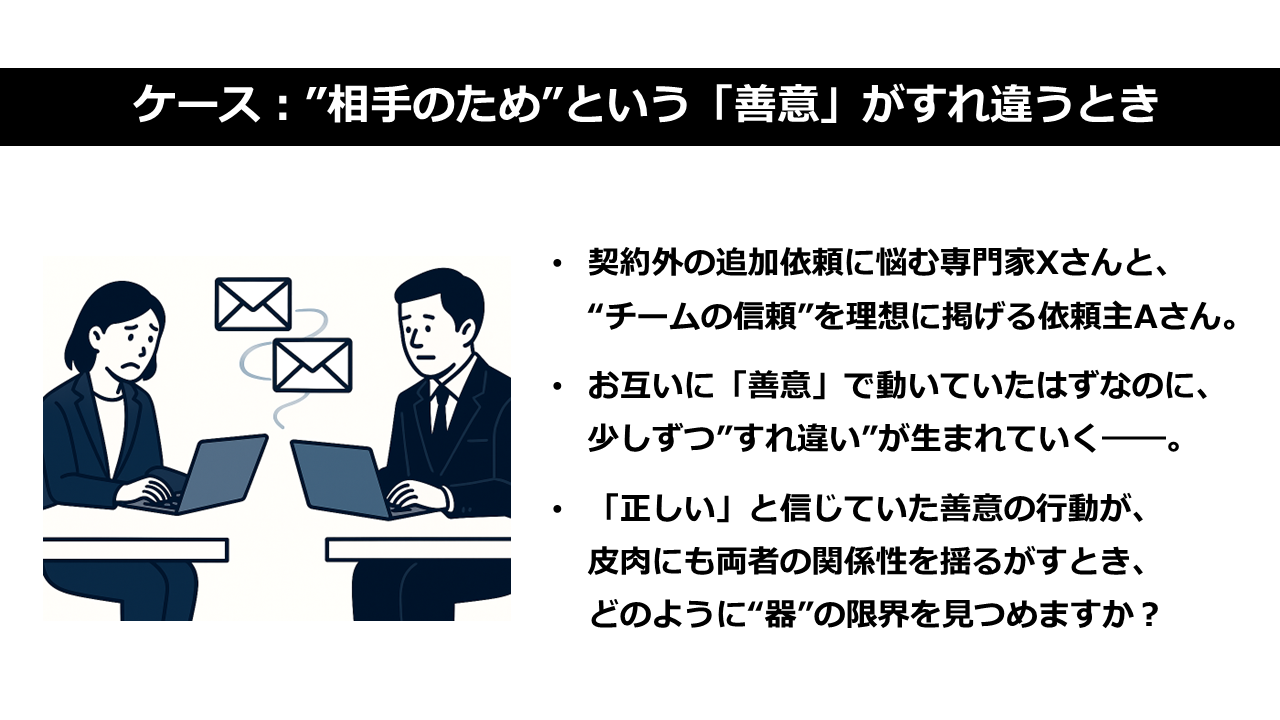「人としての器」に関する実践的な理解を深めるためのケースを作成しました。
以下、あるプロジェクトの責任者Aさんと受託者Xさんとのやり取りをみながら、「人としての器」という観点で、何が課題なのかを考えてみましょう。
ケース:”相手のため”という善意がすれ違うとき
とある企業のマネージャーであるAさんは、外部の専門家であるXさんに、新サービスに関するクリエイティブな企画を依頼しました。
3か月間のプロジェクトの前半戦が終わり、Xさんは専門性と誠実さをもって、初期の成果物を納品します。
「素晴らしい仕上がりですね。文句のつけようがありません!」
Aさんからの満足そうなメッセージを受け取ったXさんは、安堵の息をつきました。
しかし、その安堵は長くは続きませんでした。
●最初の綻び – 月曜日の夕方
プロジェクトが佳境を迎えたある月曜日の夕方、無事に二次成果物の納品も終わり、AさんはXさんに追加作業に関するメールを送信しました。
「お疲れさまです。今回の成果物も、とても良い仕上がりでした! 社内でも評価が高く、さらにブラッシュアップしたうえで、ぜひともリリースに向けて進めていきたいと思います。
ただ、急で申し訳ないのですが、社内の統一ルールに合わせて全体を再調整していただければと思います。木曜日の社内会議で使用したいです」
このときのAさんとしては、プロジェクトを成功に導くための、当然の協力依頼のつもりでした。
しかし、メールを読んだXさんの頭の中で、いくつかの疑問が渦巻きます。
(この作業は、最初の合意に入っていたかな? 契約書を見直してみよう…やはり、明記されていない。しかも、このタイミングで全体を修正するには…大幅な手戻りになる。木曜日まであと3日しかない。なぜ最初から教えてくれなかったんだろう…?)
Xさんは、コーヒーを一口飲んで、一度深呼吸しました。
感情的になることなく、長期的な関係のためにも、プロとして誠実に対応しようと心に決めます。
●プロフェッショナルの善意 – 火曜日の朝
翌朝、Xさんは、それがお互いのためになる最善の方法だと信じながら、慎重に言葉を選んで返信をします。
「いつもお世話になっております。ご連絡いただき、ありがとうございます。成果物にご満足いただけたとのこと、大変うれしく思います。
ご依頼いただいた御社の統一ルールへの再調整についてですが、こちらは当初のご契約内容には含まれていなかった作業かと存じます。大変恐縮ですが、今回は御社内でのご対応をご検討いただけますでしょうか。
もし当方での対応をご希望の場合は、追加の作業となりますため、改めて作業範囲とスケジュールについてご相談させていただければ幸いです。」
Xさんは、送信ボタンを押す前に、何度も文面を読み返しました。(言葉遣いは丁寧だし、理由も明確。これでAさんにも理解してもらえるはずだ)
しかし、その後、予想外の反応が待っていました。
●想定外のすれ違い – 火曜日の夕方
同日の夕方、Aさんから返信が届きます。
「ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。本件、貴殿による対応が難しいようでしたら、私たちで引き取らせていただきます。
また、今回の件について社内で議論した結果、Xさんのご意向次第では、今回の納品で一区切りとし、今後のご契約については一旦白紙で見直したほうがよいのでは…という意見も出ております。
Xさんとしては、今後も継続してお付き合いいただけるご意向はございますでしょうか? 率直なお気持ちをお聞かせくださいますと幸いです。」
Xさんは画面を見つめたまま、しばらく動けませんでした。
(え? なぜ急に白紙の話に? 正当な主張をしただけなのに、もしかして、やる気がないと思われた…? 相手のためを思ってプロとしての境界線を引いたつもりが、なぜ非協力的だと捉えられてしまうんだ?)
●危険な分岐点 – 水曜日の朝
翌朝、Xさんは混乱した気持ちを整理しようと、返信を書き始めました。
「正直に申し上げますと、昨日のご連絡には大変戸惑っております。私は依頼されたことを誠心誠意やってきたつもりですが、なぜ急に『白紙』ということが議題にあがったのでしょうか?
『白紙』という言葉を向けられてしまうと、正直なところ、私としても『もう退いたほうがいいのかな』という気持ちになってしまいます。
勝手ながら、今後の判断については、一旦保留にさせていただけないでしょうか…」
Xさんは、このメールを書き終えた後、一度PCから離れました。(このままメールを送ったら、関係は本当に終わってしまうかもしれない。でも、どうしてこんなことになったんだろう…?)
(以上、ケース終わり)
ここでいったん読み進めるのを止めて、XさんとAさんのそれぞれの視点から、何が起きていたのかについて、一度、ご自身で考えてみていただければ幸いです。
***
見えない心の動き – それぞれの「善意」の世界
●Aさんの心の奥底にあったもの
実は、Aさんの依頼の背景には、上司からの強いプレッシャーがありました。
プロジェクトの責任者として、何としても成功させなければならない状況に追い込まれていたのです。
(Xさんは今まで素晴らしい仕事をしてくれた。きっと、この状況を理解し、チームとして助け合ってくれるはずだ。困難を乗り越えて良い成果を出すことは、きっとお互いのためになる。)
しかし、このとき、Aさんには見落としていた部分がありました。
まず、プロジェクト開始時に「社内の統一ルール」について説明していなかったこと、そして今回の依頼が契約範囲外の作業であることへの認識が薄かった点が挙げられます。
さらに、大幅な修正を木曜日という3日後の期限で依頼するという、タイミングの問題もありました。
上司からのプレッシャーもあり、責任感の強いAさんは、Xさんの状況を十分に認識しないまま性急に対応を進めてしまいました。
その結果、Xさんからきた返信は、Aさんの期待を裏切るものとなってしまいます。
(契約に含まれていないからできない…? そんな堅いことを…。これまでの信頼関係は何だったの? もしかして、Xさんはこのプロジェクトにそもそも乗り気じゃなかったのかしら? だとしたら、無理に継続を頼むのはかえってXさんを追い込んでしまう。はっきりと意向を聞いて、もし辞めたいのなら、その選択肢を提示してあげるのが、私なりの優しさだ)
そして、Aさんは、Xさんに対する善意のつもりで配慮し、「白紙」という選択肢を提示しました。
しかし、この対応は、なぜ白紙という選択肢を提示する判断に至ったかの説明も不十分でなままで、Xさんからの正当な指摘に対する過剰で防衛的な対応だったと言えるかもしれません。
●Xさんの心の中の葛藤
一方、Xさんの心の中では、過去の苦い経験が警鐘を鳴らしていました。
(Aさんとは良い関係だ。だが、この種の曖昧な依頼を受け続けると、自分が疲弊してしまう。プロとしてきちんと線引きをすることが、健全で長期的な関係を守ることにつながる。毅然と対応して、こちらの背景を理解してもらうことは、今後の関係継続のためでもある)
Xさんもまた、健全な関係性を守るという「善意」から、プロフェッショナルとしての境界線を引きました。
しかし、振り返ってみると、Xさんにも改善の余地がありました。
契約時により詳細な要件確認を行い、「社内ルール」などの可能性について事前に質問していれば、この問題は予防できたかもしれません。
また、一方的に断るだけでなく、代替案や妥協案を積極的に提示するなど、相手の困った状況への配慮や支援の姿勢があれば、より建設的な解決につながっていたでしょう。
しかし、その後のAさんからの「白紙」という言葉によって、Xさんの善意は根底から揺さぶられることになります。
(なぜ、いきなり「白紙」なんだ? こちらの都合を考えず、追加の要求をするAさんのほうこそ配慮が欠けているのでは…? もしかして、むしろAさんのほうが関係を終わりにしたいのか? こっちは良かれと思って境界線を引いたのに、すべて裏目に出てしまった…)
最終的にXさんは感情的になり、「もう退いたほうがいいのかな」という消極的な表現で関係修復を困難にしようとしています。
プロとしての境界線を設けることはたしかに重要ですが、もう少し相手との関係継続に向けた歩み寄りの対話の継続を模索することはできたかもしれません。
なぜ「善意」は衝突するのか
このケースは、お互いの「善意が生んだ悲劇」とも言えるでしょう。
AさんもXさんも、それぞれが「相手のため」を思って行動しました。
それなのに、なぜ二人の心はすれ違ってしまったのでしょうか?
その核心として、彼らの「善意」が、自分自身の「正しさ」という器の範囲内でしか機能していなかった点が考えられます。
では、その「正しさ」は一体どこから生まれてくるのでしょうか?
その構造を解き明かすために、彼らの心の奥深くを見つめていこうと思います。
まず、二人の行動の基盤となっている「正しさ」を整理してみます。
●Xさんの正しさ:プロフェッショナルとしての誠実さ
- 前提の世界: プロの関係は、明確な契約と境界線の上に成り立つべきだ。それによって互いの領域が尊重され、長期的な関係性を守ることにつながる。
- 善意の行動: 契約外の作業は明確に断り、対等で持続可能な関係を維持しようとする。
●Aさんの正しさ:チームとしての結束
- 前提の世界: 良い関係とは、契約を超えて自主的に助け合うチームワークで成り立つべきだ。
- 善意の行動: 乗り気でない相手には、関係を清算する選択肢を「配慮」として提示するのが優しさだ。
このように、二人は異なる「正しさ」の世界に生きています。
そして、その正しさの根源を考えてみると、表面的な感情の下に隠された、より深い心の領域が見えてきます。
心の階層 – 行動の裏にある自己防衛
さらに彼らの心を、表面から深層へと掘り下げていきましょう。
●Xさんの心の階層
- 表面(困惑):「なぜ契約外の依頼を、このタイミングでしてくるのか」
- 中間(不安):「このままでは、自分の領域を侵されてしまう」
- 深層(恐怖):「また都合よく利用され、搾取されるのではないか」
●Aさんの心の階層
- 表面(困惑):「なぜこの大事な局面で、前向きに協力してくれないのか」
- 中間(不安):「チームとしての信頼を裏切られれば、プロジェクトが頓挫してしまいかねない」
- 深層(恐怖):「責任のある立場で自らの落ち度を認めたくないし、勝手に期待して、これ以上傷つくことから逃れたい」
興味深いことに、両者の行動原理は、深層にある『恐怖』や『不安』に対する自己防衛に根差しています。
Xさんの「搾取される恐怖」は、自らの専門性という聖域を守るための『境界線の正しさ』を生み出しました。
一方、Aさんの「傷つけられる恐怖」は、”チームの信頼”という理想が崩れる前に、自ら関係をリセットしようとする『配慮という名の正しさ』を形成しました。
そして、自己防衛から生まれた異なる二つの「正しさ」が、”善意”という仮面をつけて、最終的に互いを傷つけ合う結果を招きました。
深層にある恐怖や不安に気づかぬまま、自分が「正しい」と信じて取った善意の行動が、皮肉にも、相手との関係性を脅かす原因となる――ここに問題の根深い構造があります。
実践的な振り返り:より良い関係を築くために
あらためて、このケースを実践的な観点で振り返り、今後の対応としての学びを整理します。
●Xさんにとっての学び
- 予防的なコミュニケーション
・契約時に、より詳細な要件確認を行い、想定される追加作業について議論する
・「社内ルール」などの可能性について事前に質問する - 建設的な問題解決
・依頼を一方的に断るだけでなく、代替案や妥協案を積極的に提示する
・相手の困った状況に対する配慮や支援の姿勢を示す - 関係継続への配慮
・プロとしての境界線を保ちながらも、長期的な関係構築への工夫を忘れない
・Win-Winを模索する姿勢を持ち、今後の関係継続への意志を明確に伝える
●Aさんにとっての学び
- 初期設定の重要性
・契約時に「社内ルール」などの重要な制約条件は、あらかじめ洗い出して開示する
・プロジェクト要件を詳細に定義し、後から重要な条件を追加しないよう準備する - 現実的なスケジューリング
・大幅な修正が必要な場合は、十分な期間を設ける
・契約外の作業であることを理解し、追加のコストや工数を配慮したうえで提示する - 建設的なコミュニケーション
・正当な指摘に対して、まずは相手の立場や背景を理解しようと努める
・コミュニケーションを簡略化せずに、依頼の意図や背景を明確に伝える労力を惜しまない
・即座に極端な反応(「白紙見直しの提案」など)をせず、お互いの意図を対面でじっくり話し合う機会を設けるなどして、段階的に解決策を模索する
まとめ
本ケースのAさん・Xさんは、それぞれ自分なりの正しさと善意を持って、相手に向き合っていたことは疑いありません。
ただ、それがどれほど誠実であっても、人と人が関わる中では、思いがけない”すれ違い”が発生してしまうものです。
そうであるならば、むしろ、すれ違った時にこそ、器の成長に目を向ける契機として捉え直す必要があります。
このケースは、私たちに重要な問いを投げかけます。
- なぜ、私たちはこれほどまでに「自分の正しさ」に執着してしまうのでしょうか?
- その際、深層に隠れている自己防衛の動機に気づくことができるでしょうか?
- そして、本当の「器」とは、一体、何を包み込むことでしょうか?――それは、単に表面的に、相手を傷つけないようなコミュニケーションの技術を身につけることではないでしょう。
今回のケースの場合、AさんとXさんがこれからの「器」を育てるために、まず自分の「善意」や「正しさ」が、誰かを傷つけうるかもしれないという事実を引き受けることが出発点です。
そして、その正しさが、自分自身のどんな「不安」や「恐怖」から来ているのかを、冷静に見つめる勇気を持つ必要があります。
その上で、自分の中にある複雑さを認め、相手の中にも同じような複雑さがあることを想像してみることが求められます。
自分の「器」の限界を自覚し、その脆さや歪みさえも受け入れた上で、それでも、なおその縁を超えて相手の世界に手を伸ばそうと試み続ける意志を持つ――この姿勢こそが、真に深い関係を育むことにつながっていきます。
今日、誰かとの関係で小さなすれ違いを感じたとしたら、それは相手を責める材料ではなく、あなたの「正しさ」と、その奥にある「不安」や「恐怖」の輪郭を教えてくれるサインかもしれません。
そのとき、「なぜ私はこう感じるのだろう?」と心の奥を見つめると同時に、こう問いかけてみてはいかがでしょうか。
「相手は、どんな“不安・恐怖”を抱え、どんな“正しさ”の世界で、私のためを思い、私たちのためを思ってくれているのだろう?」
そこに完璧な正解があるわけではありませんし、一生懸命に向き合っても、時には傷つけあう結果になるかもしれません。
そして、たとえ傷つけ合ったとしても、その痛みの中から再び相手を理解しようと何度も手を伸ばしていく――その絶え間ない関係構築のプロセスこそが尊いものであるように思います。