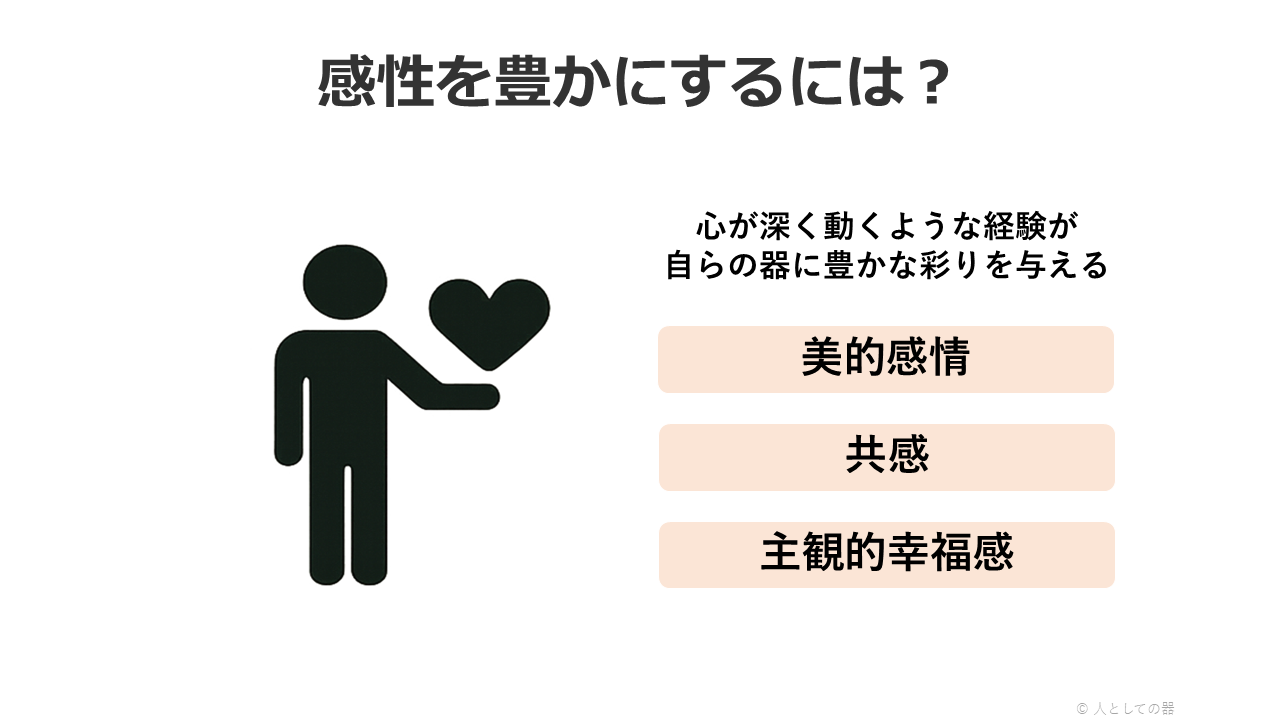美しい景色に息をのんだり、素敵な音楽に涙したり、誰かの気持ちに深く寄り添ったり――私たちは日常の中で、心が動かされる瞬間に出会い、「感性」を働かせます。
感性とは、辞書的には「物事を心に深く感じ取る働き。感受性」と説明されますが、それは単に外部からの刺激に敏感であることだけを意味するわけではありません。
近年の心理学分野の研究では、「感性」が私たちの幸福感(ウェルビーイング)、他者とのつながり(共感)、そして世界の美しさや意味を深く味わう能力(美的感情)と深く関わっていることを示唆しています。
感性は、人生を彩り豊かに生きるための大切な要素です。
この記事では、最新の心理学的知見に基づき、「感性とは何か」、そして「どうすれば日々の生活の中で感性を育み、豊かにしていくことができるのか」について紹介します。
感性とは? – 多面的な心のアンテナ
感性は、私たちの心の奥深くにある、世界や他者、そして自分自身とつながるためのアンテナのようなものです。
近年の心理学分野の研究レビューによって特定された、豊かな感性を磨くうえでの3つの重要な側面を紹介します。
① 美的感情(Aesthetic Emotions)
美的感情とは、「対象の美的魅力や美徳を知覚し評価する際に生じうる感情」(Schindler et al., 2017)です。
感性豊かな人は芸術、自然、デザインなど多様な対象に対して、単なる「きれい」という感想を超えた、複雑で豊かな美的感情を抱きます。
- 多様な美的感情のスペクトル: Schindler et al.(2017)は、21種類の美的感情を同定しました。これらは、美しさの感覚、感動、魅了、畏敬の念などの「典型的な美的感情」、喜びやユーモアなどの「楽しい感情」、興味や洞察などの「知的情動」、そして醜さや退屈などの「ネガティブな美的感情」まで多岐にわたります。
- 複雑さと混合性: 美的感情の特徴的な点は、そのしばしば矛盾した複雑な性質にあります。Menninghaus et al.(2019)によれば、美的感情は本質的に「内在的な快さ」を含みますが、同時に不快な要素(例:悲しい音楽から生じる感動)を統合することもあります。この複雑性や混合性こそが、美的体験をより豊かで深いものにします。
②共感(Empathy)
共感は、他者の心に寄り添い理解する能力で、感性を働かせる重要な側面です。
共感には様々な定義が提案されていますが、Håkansson Eklund & Summer Meranius(2021)の包括的レビューによれば、4つの中心的要素があります。
- 理解(Understanding): 他者の感情状態や視点を知的に把握すること
- 感情(Feeling): 他者の感情状態に応じた感情的反応を持つこと
- 共有(Sharing): 他者と類似した感情を経験し共有すること
- 自己-他者分離(Self-other differentiation): 共有された感情が自分の感情なのか他者の感情なのかを区別すること
これら4つの要素に基づき、共感とは「自他を分離したうえで、他者が感じていることを理解し、感じ、共有すること」と定義されます。
そのうえで、同論文では、(1)共感は親密さと距離の両方である、(2)共感は感情と認知の両方である、(3)共感は身体と心の両方であることを指摘しています。
本記事では、感性という観点から、あくまで感情(Feeling)面の共感に焦点を当てますが、現実的には、認知的共感と切り離して考えることはできません。
この点に関して、Cuff et al.(2016)による共感の概念レビューの中でも、以下のポイントが指摘されています。
- 共感と同情の区別: 共感(Empathy: “相手と同じように感じる”)と同情(Sympathy: “相手のために感じる”)は明確に区別される必要があります。共感では相手と類似した感情を共有するのに対し、同情では「可哀そう」「気の毒」といった、相手の感情とは異なる反応が生じます。この区別は、対等な関係性を保つ上で重要です。
- 認知的共感と感情的共感の統合: 両者は別々の能力ではなく、相互に影響し合う関連した側面です。例えば、相手の気持ちを考えることで感情が動き、感情が動くことで理解が深まるという循環的関係があります。
- 自己と他者の区別: 共感は、感情の共有がありながらも「自己-他者分離」を維持します。この区別が感情伝染(他者の感情に巻き込まれて自他の区別が失われる状態)と共感を分ける重要な境界線と言えます。適切な距離感を保ちながら他者の感情を理解し共有することで、健全な共感が可能になります。
上記のとおり、共感は、親密さ(共有)と距離感(分離)、感情と認知、身体と精神の両側面を持つ統合的概念と言えるでしょう。
(※本記事では、「感性」に着目した共感に焦点を当てますが、これは前回の記事で触れた「自制」と矛盾しがちであり、実際には両者を統合して考える必要があります。また、感情は認知とも密接に関連します。このように共感を多面的に統合して捉えることは非常に重要ですが、議論が複雑になるため、あらためて別の記事で触れたいと思います。)
③主観的幸福感(ポジティブ感情)
感性は、日常生活における豊かなポジティブ感情の体験と深く関わっています。
Diener et al.(2018)によれば、主観的幸福感(Subjective Well-being: SWB)は「本人の視点からの人生の質に対する総合的な評価」と定義され、認知的要素(人生満足度)と感情的要素(ポジティブ・ネガティブ感情の体験)の両方を含みます。
感性豊かな人は、より多様で豊かなポジティブ感情を体験する傾向があります。
- 感情の精緻化: ポジティブ感情をより細かく区別し、その複雑さを理解することを感情の精緻化と呼びます。感情の精緻化により、単に「嬉しい」と感じるだけでなく、「満足」「興奮」「穏やかな喜び」「達成感」などの微妙な違いを認識できるようになります。研究によれば、ポジティブ感情の精緻化と心理的レジリエンスは関連が高いことが示唆されています(Tugade et al., 2004)。
- 文化的に形作られる感情体験: 文化によってポジティブ感情の体験や価値づけは異なります。例えば、Hitokoto & Uchida(2015)が提案する「協調的幸福感」の研究では、東アジアの文化圏では「他者との関係志向的な喜び」「興奮よりも平穏な満足感」「集団内の調和に基づく安心感」などを重視する特徴が示されています。
さらに、感性豊かな人は、ポジティブな経験を単に体験するだけでなく、それを「セイバリング(味わう)」する能力に優れています。
Bryant, Chadwick, & Kluwe (2011)によれば、セイバリングは「ポジティブな経験に注意を向け、それを評価し、維持し、高める過程」と定義されます。
Quoidbach et al. (2010)は、ポジティブ感情を高める4つのセイバリング戦略を提示しました。
- 行動的表現 (Behavioral Display): 笑顔、声を上げる、跳ね回るなど、ポジティブな感情を身体的に表現する
- 現在への注意の焦点化 (Being Present): 今この瞬間に集中し、マインドフルな状態で体験する
- 祝福 (Capitalizing): ポジティブな出来事を他者と共有する
- ポジティブなメンタルタイムトラベル (Positive Mental Time Travel): 過去または未来のポジティブな出来事について考える
この研究からは、多様なセイバリング戦略の採用が全体的な幸福感と強く関連していることが示唆されています。
つまり、一つの戦略に頼るよりも、個々人の状況に応じて様々な味わい戦略を柔軟に使い分けられることが大切になります。
感性を豊かにする3つのヒント
感性は、生まれ持った才能でなく、意識的な取り組みによって育むことができます。
どうすれば感性を育むことができるか――研究から示唆される3つのヒントをご紹介します。
1:美や感動に積極的に触れる【美的体験の活用】
美しいものや心を動かすものに触れることは、感性を養うための最も直接的な方法の一つです。
実践のポイント:
- 多様な美的体験: 美術館、コンサートホール、映画館、自然の中など、様々な場所に足を運び、五感を刺激する体験を意識的に増やします。
- 感情に名前をつける: 美的体験をした際に感じた感情を具体的に言語化してみましょう。「畏敬」「魅了」「懐かしさ」「安らぎ」など、美的感情の研究で使われる言葉を参考に、自分の感情のニュアンスを捉える練習をします。
- 美的評価を深める: なぜそれに心を動かされたのか、どこに美しさや価値を感じたのかを考えてみることで、美的感情の能力が磨かれます。
- 複雑な感情を味わう: 喜びだけでなく、時に悲しみや畏怖を含む複雑な美的体験も、感性を豊かにする重要な要素です。
2:他者の心に寄り添う練習をする【共感力の育成】
共感は、他者との間に温かい心のつながりを生み出し、感性を育む重要な側面です。
共感力を高めるための意識的な練習機会をつくることが重要になります。
実践のポイント:
- 共感と同情を区別する: 相手と同じような感情を共有する(共感)ことと、相手を可哀そうに思う(同情)ことの違いを理解します。真の共感では相手の視点に立ち、対等な関係性が保たれます。
- 非言語コミュニケーションに注意を払う: 言葉だけでなく、表情、声のトーン、身振りなどからも感情を読み取る練習をします。
- 認知的共感を育てる: 相手がなぜそう感じているのか、その人の立場や状況に立って、見えないナラティブ(物語)を想像してみることも大切です。背景の物語を知るという認知的共感を通じて、感情的共感も磨かれていきます。
- 自己と他者の距離感のバランスを学ぶ: 相手の感情を共有しながらも、自己と他者を区別する「自己-他者分離」も意識します。これにより、過度に相手の感情に巻き込まれすぎず、より健全な共感が可能になります。
3:日常のポジティブな瞬間を意識的に「味わう」【幸福感の増幅】
感性は、特別な体験だけでなく、日常の中のささやかな喜びや美しさを感じ取る力でもあります。
ポジティブな感情や経験を意識的に「味わう」ことで、幸福感を高め、感性を磨くことができます。
実践のポイント:
- 感覚を味わう: ポジティブな経験をしているとき、その瞬間の身体感覚や思考に注意を向け、味わい尽くします(セイバリング)。例えば、美味しい食事をするとき、その香り、味、食感などを意識的に感じ取ります。また行動的表現として、笑顔、声を上げる、跳ね回るなど、身体的に表現することも大切です。
- 過去と未来を語り合う:過去または未来のポジティブな出来事について考えることで感性も磨かれます。過去にどんなポジティブな経験をしたのか、ワクワクする未来に向けた何がしたいのかを、じっくりと語り合う機会を設けましょう。
- 文化的な幸福のあり方を尊重する: 文化によって幸福の捉え方は異なります。集団との関係を重視する東洋文化の場合、日々の感謝の実践(感謝日記や感謝の手紙)や、良い出来事を他者と積極的に共有することで、ポジティブ感情が増幅されます。
まとめ:感性は器の彩り
感性は、特別な能力ではなく、意識的な心がけと実践によって、誰もが育むことができます。
美的感情、共感、主観的幸福感(ポジティブ感情)といった要素は互いに関連し合い、感性の質を高める基盤となります。
- 美しいものや心を動かすものに触れ、多様な美的感情を体験する
- 他者の気持ちに寄り添い、共感と自己-他者分離のバランスを保つ
- 日常のポジティブな瞬間を意識的に味わい、特に日本文化の場合、他者とともに感性を育む
これらのヒントを参考に、ぜひあなたの「感性」を豊かにする一歩を踏み出してみてください。
心が深く動くような経験が、私たちの器に豊かな彩りをもたらし、当たり前の日常をより輝かせてくれるでしょう。
参考文献
- Bryant, F. B., Chadwick, E. D., & Kluwe, K. (2011). Understanding the processes that regulate positive emotional experience: Unsolved problems and future directions for theory and research on savoring. International Journal of Wellbeing, 1(1), 107-126.
- Cuff, B. M. P., et al. (2016). Empathy: A Review of the Concept. Emotion Review, 8(2), 144–153.
- Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2018). Advances and Open Questions in the Science of Subjective Well-Being. Collabra: Psychology, 4(1): 15.
- Håkansson Eklund, J., & Summer Meranius, M. (2021). Toward a consensus on the nature of empathy: A review of reviews. Patient Education and Counseling, 104(2), 300–307.
- Hitokoto, H., & Uchida, Y. (2015). Interdependent Happiness: Theoretical Importance and Measurement Validity. Journal of Happiness Studies, 16, 211–239.
- Menninghaus, W., et al. (2019). What Are Aesthetic Emotions? Psychological Review, 126(2), 171–195.
- Quoidbach, J., Berry, E. V., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2010). Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and Individual Differences, 49(5), 368–373.
- Schindler, I., et al. (2017). Measuring aesthetic emotions: A review of the literature and a new assessment tool. PLoS ONE, 12(6): e0178899.
- Tugade, M. M., Fredrickson, B. L., & Barrett, L. F. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72, 1161–1190.