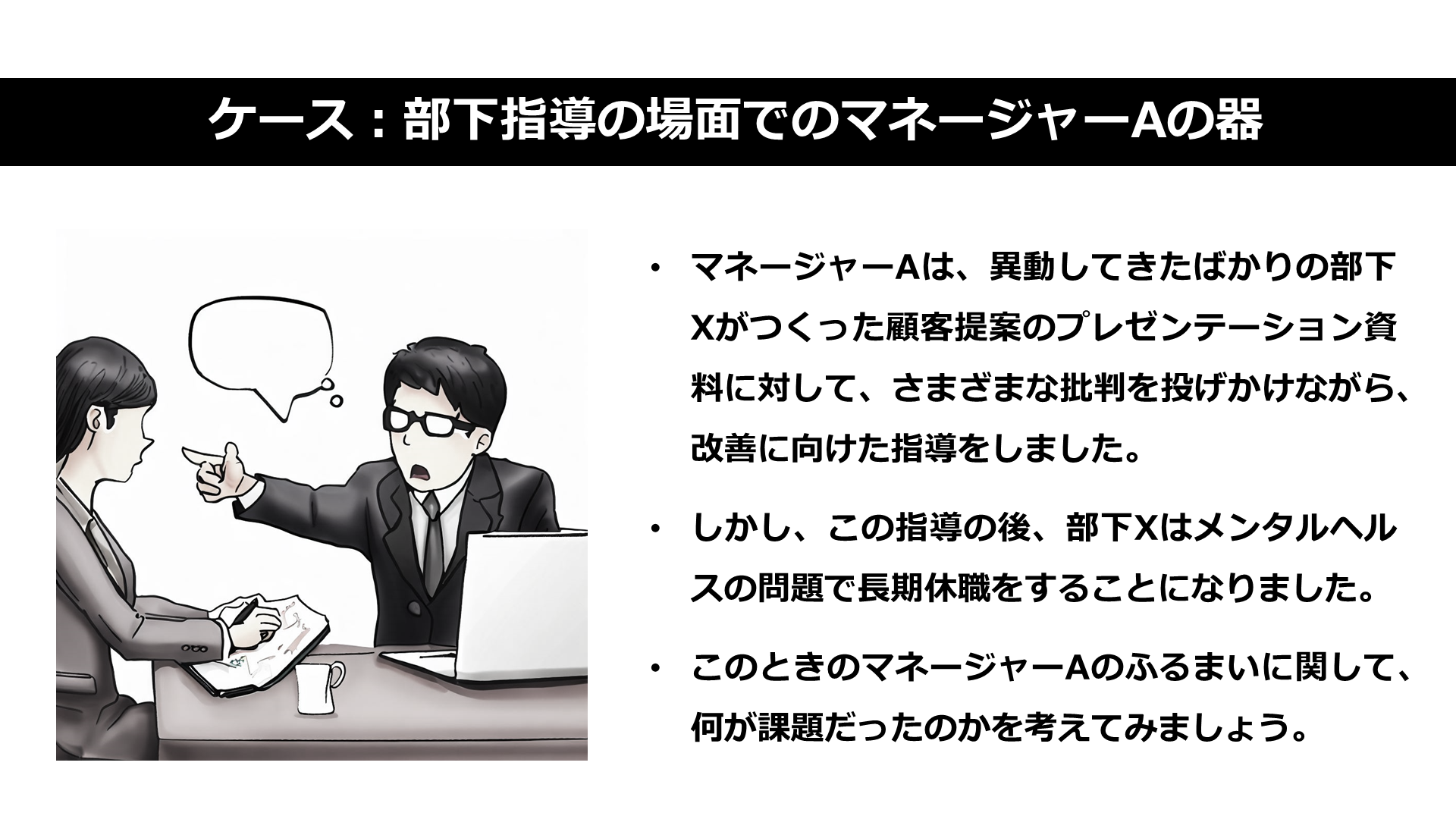「人としての器」に関する実践的な理解を深めるためのケースを作成しました。
以下、部下指導の場面でのマネージャーAのふるまいをみながら、「人としての器」という観点で、何が課題なのかを考えてみましょう。
ケース:部下指導の場面でのマネージャーAのふるまい
【状況】
ある企業においてマネージャーAは、3人の部下を持っています。
30代前半の部下Xは、先月、調査研究グループからサービス開発グループに異動してきました。
この日、部下Xが、初めて自分で企画した顧客向けの研修コンテンツのプレゼン資料をマネージャーAのもとに持ってきました。
マネージャーAは、部下Xを管理職候補として自律的に組織・チームをリードする人材に育てたいと考えています。
しかし、部下Xは、どこか他者依存で、上司(マネージャーA)に言われたことばかりをやっており、淡々と仕事もこなす感じにも見受けられます。
マネージャーAは、部下が自らビジョンを描いたり、積極的に提案したり、率先して周りを巻き込む姿勢を持たないことに課題意識を持っています。
一方、マネージャーA自身は、部下育成に関して独自にコーチングやクリティカルシンキングを学び、日常的にスキルを高めてきました。
そこで、マネージャーAはこれまで自分で学んできたことを実践しようと、部下Xにフィードバックを行う時間をつくり、研修コンテンツのプレゼン資料の改善に向けた指導をすることにしました。
マネージャーA:
一通りプレゼンの説明をしてもらったけれど、自分ではどのあたりがうまくいっていると思う?
部下X:
今回の研修では「人としての器」をテーマにしました。
一般的なマネジメント研修では知識・スキル中心で、即効性のあるツールやフレームワークを学ぶものが中心ですが、「人としての器」をテーマとしたものはほとんど見られません。
今回の研修を通して、時間をかけてじっくりと「器」という観点から自分自身を振り返ることになり、それは受講者にとっても貴重な機会になると思います。
マネージャーA:
この研修を行うと、顧客からはどういった反応があると思う?
部下X:
まずは器という概念を理解して、それから自身の器の成長についてグループで対話を通じて、自分がどういった器をつくろうかという理想の状態を描くことになります。その後、そのためのアクションプランをつくるので、受講者も前向きに成長に向けた一歩を踏み出すことが期待されます。
マネージャーA:
本当に、こちら側が意図したとおりにうまく行くかな?
部下X:
それは受講者の研修に臨む態度や置かれた文脈にもよるかもしれませんが、この研修は1日という制約の中で、できるだけ多くの受講者が自分にとっての「器」に目を向けられるように、対話時間をしっかりと取ったり、内省のツールとしてのワークシートを用意するなどの工夫をしました。
マネージャーA:
それって、つまり、参加者が内省する力があるかどうかにかかっているということ?
もしそうだとしたら、プログラムの設計として少し弱すぎないかな?
調査研究グループではそういった仕事のクオリティでも許されたかもしれないけれど、この仕事はお客さんからお金をもらってやるものだからさ。
受講者がどう感じるかに関しては、こちら側の想定どおりに行くとは限らないから、できるだけ響かなそうな人をイメージしながらプログラムをつくったほうがいいよ。
部下X:
たしかに、そうですが、響かなそうな人をターゲットとした場合は、コンテンツ全体のレベルもそういう人に合わせることになるので、逆にメインターゲットの満足度が下がってしまいかねないと思います。
響かなそうな人は、今回の集合研修のターゲットとせずに、別の個人面談などがある研修コンテンツなどで受け皿を用意したほうが良いのではと考えています。
マネージャーA:
それはそうなんだけど、俺が言っているのは、この研修で期待される効果がいまいちはっきりしていないってことなのよ。
本当にこの研修を通じて、顧客に最大の効果は発揮されると思うの?
そもそも君が想定している効果って何?
その効果を最大にするための工夫が、現状では内省任せになっていて、プログラムの完成度としては不十分なんじゃないの?
やみくもに反論したり言い訳したりする前に、相手が何を考えて伝えようとしているのかを深堀りして尋ねたほうがいいよ。
その真意をきちんと理解しないまま会話していると、顧客に対しても質の高いプレゼンテーションはできないからさ。
明日までに、もう一度、提案資料は考え直してもってきてください。
この時、部下XはマネージャーAの言葉をただ受け入れる様子で、それ以上の返答をすることができませんでした。
しかし、この指導の翌日以降、部下Xは会社を欠席するようになり、その後、メンタルヘルス不調で仕事を長期休職する運びになりました。
マネージャーAは、部下Xをリーダー候補として期待して指導をしたつもりだったのですが、「なんだか最近の若者は打たれ弱すぎて困るな…」と溜息をつきました。
(以上、ケース終わり)
上記のケースをご覧いただいて、どのように感じたでしょうか?
マネージャーAの発言内容は説得力があり、仕事のクオリティをあげるうえで非常に重要な観点が含まれていたようにも思えます。
しかし、この指導を引き金にして、部下Xがメンタルを崩してしまったことは明らかと言えます。
みなさんは、上記のケースにおいて、マネージャーAの姿勢にどのような課題があったと思われますでしょうか?
ここで読み進めるのを止めて、一度、ご自身で考えてみていただけますと幸いです。
***
マネージャーAは、クリティカルシンキング(批判的思考)に長けており、いくつかの問いを投げかけて部下Xの自律的な思考を引き出そうとしています。
そのことは、「自分ではどのあたりがうまくいっていると思う?」「本当に、こちらがら意図したとおりにうまく行くかな?」「プログラムのつくりとして少し弱すぎないかな?」「本当にこの研修を通じて、顧客に最大の効果は発揮されると思うの?」「そもそも君が想定している効果って何?」「プログラムの完成度としては不十分なんじゃないの?」という質問に象徴されます。
しかし、こうした問いは、マネージャーAがこれまで身につけたフレームワークが活かされているものの、どこか表面をかすめるだけで核心をついていない印象もあります。
そして、結果として、部下Xが他者依存的になり、上司(マネージャーA)に言われたことばかりをやるようになり、淡々と仕事もこなす感じに見受けられる現状を引き出しているようにも思えます。
こうなってしまったのは、なぜでしょうか?
一つには、マネージャーAが投げかける問いが、自分なりの正解を想定していて、その正解を当てられない部下Xは能力がない人間であると思わせるやりとりになっていることが考えられます。
マネージャーAは部下Xの可能性を引き出すというよりも、むしろ部下Xの可能性を狭めていると言えるのです。
以前、ビジネスにおける「さしすせそ」の病という記事の中で、「最善策」「証拠」「スキル」「説明性」「即効性」を求めすぎることの弊害について触れました。
マネージャーAは不確実性を減らし、成功確率を上げるために、繰り返し批判的な投げかけを行っていますが、それによって見失っているものが多くあることに気づけていません。
それは、マネージャーAが仕事のクオリティばかりに気をとられて、部下X自身のことをきちんと見ようとしていないと言い換えることもできます。
マネージャーAは、部下Xがどのような想いで新しい研修コンテンツを持ってきたかを、どれほど深く理解しようと努めていたと言えるでしょうか?
残念ながら、マネージャーAは部下Xの想いに関して汲み取ろうとする共感的な投げかけは、ほとんどありませんでした。
さらに、マネージャーAは、クリティカルシンキング(批判的思考)には長けていますが、コンストラクティブシンキング(建設的思考)を十分に身につけられているとは言えません。
部下指導の場面では、批判的なコメントだけでなく、「○○をしてみたらもっと良くなると思うよ」「私が責任を取るから○○にもチャレンジしてみたら?」と建設的に発展させるような姿勢も重要となります。
しかし、マネージャーAは批判的なコメントを投げかけることに終始し、結果として自分のほうが正解をわかっている優位な立場であると思わせることに成功しているかもしれませんが、部下のほうから恐れずに提案ができるような対等な関係づくりには失敗していると考えられます。
そのような中で、徐々に部下が委縮し、上司の顔色を伺ってばかりで、自分の意見も率直に言えなくなり、そして、やがてメンタルを疲弊して休職に至ってしまったのも当然の結果と言えるのではないでしょうか。
まとめ
以前の記事、「人としての器」の評価をどう考えるか?の中でも述べましたが、私たちが世界をどのように捉えるかに関しては、実証主義・解釈主義・批判的実在論といったパラダイムがあります。
その中でも、特に現代社会で根強いのは実証主義のパラダイムと言えます。
これは、一言で言えば、誰が見ても同一の結論となるように客観的に事象を捉えるという思想の下で、普遍的な真理を追い求め、その真理が成り立つ条件を事細かに規定しようという立場です。
それゆえに、世界をクローズドシステム(閉鎖空間)と見なして、ある刺激を与えれば画一的な反応が出る機械のように動くものと捉える傾向に陥ることがあります。
しかし、社会科学に代表されるような人間社会の現実は、複雑なオープンシステム(開放空間)であり、様々な不確実性に満ちているという前提を持っています。
マネージャーAのように「本当に、こちら側が意図したとおりにうまく行くかな?」という問いは、実証主義のような普遍的な真理が成り立つことを念頭にしていると考えられるでしょう。
もしオープンシステムであるという前提が共有できていたのならば、そもそも「意図したとおりに成功させる」ことは不可能だと理解したうえで、もう少し違った質問の仕方になるかもしれません。
例えば、「こちら側が意図したとおりにうまく行かない可能性もある。もう少し、顧客に寄り添った形で研修効果を高めることはできないかな?」という質問の仕方であれば、不確実性を前提とした認識が共有されることになります。
些細な違いのように見えるかもしれませんが、もともとのパラダイムが異なるがゆえに質問の仕方にも微妙なニュアンスの違いが表れており、それが結果としては、相手の主体性を引き出すかどうかに関わる大きな違いを生じさせるのです。
これに対して、マネージャーAの場合は、クローズドシステムを前提としているため、真実を目指してできるだけ不確実性を排除するために、事細かに内容を詰めるような指導をしていくことになるでしょう。
それは一方で、現実の複雑さのダイナミズムや、長期的な視野や、目に見えない可能性を見落とすことになるかもしれません。
そして何より、部下Xがどのように自主性を発揮する形で変容をしていくか、その結果として、もしかしたら上司であるマネージャーAが見えている以上にコンテンツ自体が発展していくかもしれない可能性を狭めることにもなります。
このように、私たちが自分の置かれたパラダイムに束縛されているときこそ、「人としての器」の在り方に意識を向けることが重要と言えます。
「感情」「他者への態度」「自我統合」「世界の認知」という四領域の観点から自分の器を省みることできれば、自分の価値基準にとらわれて相手を説得したり、相手の意見に耳を傾けようとしないという過ちを防ぐことができます。
そこで、あなたがマネージャーAになりきったつもりで、以下の問いを考えてみてください。
- 部下Xと接するとき、あなたはどのような「感情」を抱いていますか? 感情豊かにポジティブなフィードバックができているでしょうか?
- 部下Xと接するとき、あなたはどのような「他者への態度」で接していますか? 真剣に相手の話や想いに耳を傾けようとしているでしょうか?
- 部下Xと接するとき、あなたはどのような「自我統合」の過程にありますか? 自身の信念やありたい姿も真摯にさらけ出して伝えているでしょうか?
- 部下Xと接するとき、あなたはどのような「世界の認知」を持っていますか? 広い視野から様々な可能性を検討しようとしているでしょうか?
こうした実践を積むことで、少しずつ相手の想いを汲み取りながら、相手の自主性を促すような指導やフィードバックができるようになるでしょう。
先日、「仏様の指」というお話を聴くことがあり、あらためて部下指導の心得について考えさせられました。
「仏様がある時、道ばたに立っていらっしゃると、一人の男が荷物をいっぱいに積んだ車を引いて通りかかった。
そこはたいへんなぬかるみであった。
車は、そのぬかるみにはまってしまって、男は懸命に引くけれども、車は動こうともしない。
男は汗びっしょりになって苦しんでいる。
いつまでたっても、どうしても車は抜けない。
その時、仏様は、しばらく男のようすを見ていらっしゃいましたが、ちょっと指でその車におふれになった、その瞬間、車はすっとぬかるみから抜けて、からからと引いていってしまった」「これがほんとうの一級の教師だ。男はみ仏の指の力にあずかったことを永遠に知らない。自分が努力して、ついに引き得たという自信と喜びで、その車を引いていったのだ」
大村はま『教えるということ』より
仏様の指の力が強すぎたら、その男は仏様の指に気づいて、仏様に感謝して終わったかもしれません。
逆に、仏様の指の力が弱すぎたら、男はいつまでもぬかるみから出られず、これからずっと自信を失っていたかもしれません。
マネージャーの役割として重要なのは、仏様のようにさりげなく、部下の成長に向けて背中を押すことではないでしょうか。
「人としての器」を学び実践することは、そのような姿勢で他者と向き合うことに他なりません。
マネージャーAが、部下に自らのビジョンを描かせ、積極的に提案をさせ、率先して周りを巻き込む姿勢を持たせられないかと課題意識を持っていること自体は素晴らしいことです。
しかし、そのような部下育成の想いを持っているにもかかわらず、どういうわけか部下が自律的にならずに閉塞感が漂っているのだとしたら、マネージャー自身が、一度、スキルやテクニックといった形式知化できるものばかりを獲得する姿勢から離れる必要があります。
そうしたときこそ、正解のない不確実で曖昧な「人としての器」という概念に目を向けるべきタイミングと言えるのかもしれません。