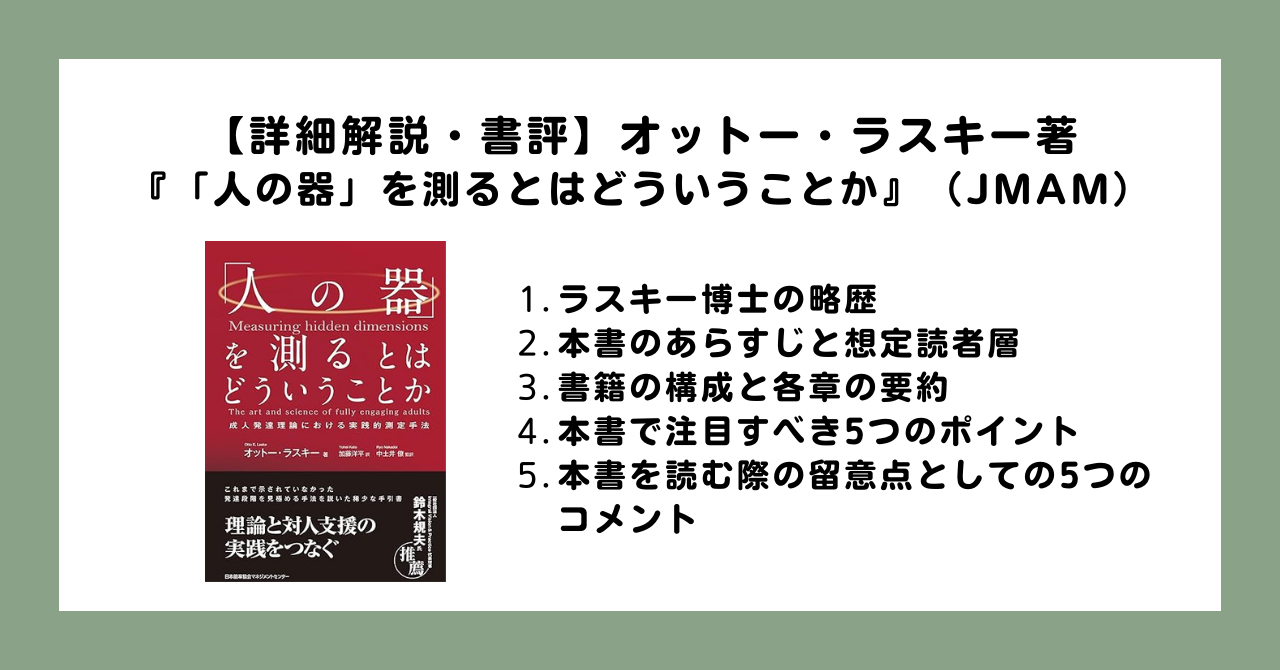2024年2月末、オットー・ラスキー著『「人の器」を測るとはどういうことか』がJMAM(日本能率協会マネジメントセンター)から刊行されました。
監訳者の中土井僚氏によれば、発売開始3週間で重版が決まったとのことで、にわかに注目を集めています。
「人としての器」を研究する私たちから見ても、今後の「器」という概念の広がりを期待させるタイトル・内容であり、私は発売開始直後に一読し、少し時間をおいてから再読しました。
目に見える成果やスキル・テクニックばかりが評価されがちな現代社会に生じている様々な課題を克服するために、「器」という一見わかりづらいものを見ようとする姿勢は、今後、より一層に大切になると思います。
本書の所感を簡潔に言えば、気軽に読めるほど簡単な内容ではないものの、誰もが読むべき価値のある一冊です。
特に他者に影響を与える立場にあるビジネスパーソン――経営者、管理職、人事部、コーチ、コンサルタントなどに該当する方は、本書の内容を深く噛みしめることによって、自分を取り巻く世界や他者に対する向き合い方に大きな変容をもたらしてくれるのではないかと思います。
ただし、本書は実務書という位置づけであるものの、専門書に近い内容であり、前提知識がないと読み進めることが難しいかもしれません。
そこで、今回の記事では、以下の5つのトピックにより、本書を挫折せずに読み進められるようなガイドを提供できればと思います。
- ①ラスキー博士の略歴
- ②本書のあらすじと想定読者層
- ③書籍の構成と各章の要約
- ④本書で注目すべき5つのポイント
- ⑤本書を読む際の留意点としての5つのコメント
①ラスキー博士の略歴
ラスキー博士に関する出版社の著者紹介はこちらです。
米国マサチューセッツ州グロスター、インターデベロップメントインスティチュート(IDM)創設者兼ディレクター。社会科学の学者であると同時に、発達コーチ、チーム開発者/ファシリテーターとしても知られている。成人の発達、特に生涯にわたる成人の社会性と情動の発達、認知の発達に関する数冊の著書がある。また国際的な出版物やブログ(www.interdevelopmentals.org)に掲載された多くの論文やCDF(Constructive Developmental Framework:構成的発達フレームワーク)の指導者としても知られている。社会科学の研究に加え、作曲家、詩人、ビジュアルアーティストとしても活動している。
こちらの記事も参考にしつつ、略歴をざっくりまとめてみると以下のとおりになります。
- 1936年4月にポーランドで生まれる(今年で88歳!)
- 20代:ホルクハイマーやアドルノに師事し、弁証法を学び博士号を取得
- 20代以降:詩や音楽をつくり続け、30代前半でボストン (米国) のニューイングランド音楽院に在籍し作曲の修士号を取得
- 30~50代半ば:人工知能やコンピューターサイエンス領域の准教授や客員教授やコンサルタントとして活躍
- 50代半ば以降:ハーバード大学教育大学院で発達理論を学び直し、さらにマサチューセッツ専門心理学校で臨床心理学を学び心理博士号を取得
- 60代半ば以降:インターデベロップメントインスティチュート(IDM)を創設し、発達コンサルティングとコーチングの学術的・実践的な基盤を確立
年齢を重ねても新しい分野に挑み続けて学び続ける姿勢が素晴らしいですね。
また特筆すべき点は、サイエンスとともにアートにも深い造詣があるところです。
なお、本書の英語版のサブタイトルは「The art and science of fully engaging adults」とあり、直訳すると大人に十分に関わるためのアート(芸術的な技術)とサイエンスとなり、サイエンスだけでは捉えきれないものを大切にしているラスキー博士の意図を感じ取ることができます。
ちなみに、ラスキー博士の作品はこちらからご覧になれます。
・詩と曲:http://www.ottolaske.com/homepage.html
・ビジュアル作品:https://www.rockportartassn.org/otto-laske
なお、コーチ仲間の高橋美佐さんがラスキー博士について「88歳を超えてなお輝く、多才な学者の足跡」と素晴らしいイントロダクションをされていますので、美佐さんが書かれた記事も併せてご覧くださいますと幸いです。
②本書のあらすじと想定読者層
本書の主題は「社会的・感情的発達」と呼ばれる領域であり、ロバート・キーガンの発達理論に立脚し、キーガンの測定手法をより実践的に洗練している点に特徴があります。
本書の表紙裏には次のような記述があります。
「多くの人たちは発達段階の評価・測定に関して、それらをテストのようなものとみなすような歪められた見解を持っているように思われます。しかし、実際の測定は、実証主義的なインタビュー・メソッドに基づいており、ある種の定性分析なのです」
この記述の大意として、誰でもできるような再現性があって客観性も担保される手間のかからないテストのような形で発達段階の評価・測定は幻想であり、インタビューを通じた豊かな語りという定性情報を用いることで、初めて妥当性のある測定が可能になると指摘している点には強く賛同できます。
言い換えれば、本書では、一見わかりづらく曖昧にされていた人の発達(あるいは器)の概念を詳細に踏み込んで記述しており、さらにその測定に関するインタビューと分析の方法論を、精緻に解像度高く述べているところが特徴です。
それゆえ想定される読者としては発達支援に携わる人、例えば、人材育成の専門家、組織開発の専門家、コーチ、プロセスコンサルタント、キャリアカウンセラーなど、またマネジメントの立場にある者、人事部、経営層、士業、親、先生・教育者など他者に影響を与える立場にある読者にとって、本書は重大な視点をもたらすと思います。
なお、序文では、本書が主として「社会的・感情的発達」の領域に焦点を当てた第1巻であり、あわせて「認知的発達(弁証法思考)」について詳述している第2巻を読むことで、はじめて人の発達を包括的に理解できると述べられている点にも留意が必要です。
ちなみにラスキー博士の発達モデルは、上記の2領域に加えて本書第十章で述べている「欲求/圧力分析」があり、さらに統合的な視点である「精神性(スピリチュアリティ)」の領域の合計4領域で発達のプロファイリングを行うとされます。
この点で、繰り返しになりますが、本書では「社会的・感情的発達」をメインに扱っているため、本書の内容だけで人の発達(あるいは器)を包括的に理解することはできないという点は心に留めておく必要があるでしょう。
上述の通り、「社会的・感情的発達」はキーガンの発達理論に立脚しています。
そのため、前提知識として、キーガンの発達理論に言及した加藤洋平氏や中土井僚氏が関わっている成人発達理論の関連書籍をあらかじめ読んでおくと、導入的理解として役立つのではないかと思います。
・『なぜ人と組織は変われないのか』英治出版
・『なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか』英治出版
・『なぜ部下とうまくいかないのか』日本能率協会マネジメントセンター
詳細は本書をお読みいただければと思いますが、キーガンの発達段階モデルは「段階2:手段・道具的段階」「段階3:他者依存段階」「段階4:自己著述段階」「段階5:自己認識段階」の四段階で構成され、本書の中で繰り返し強調される表(本書のP35より、一部修正して引用)は次のとおりです。
| 発達段階 の変遷 | 段階2 手段・道具的段階 | 段階3 他者依存段階 | 段階4 自己著述段階 | 段階5 自己認識段階 |
|---|---|---|---|---|
| 他者の捉え方 | 自己の欲求を満たすための手段・道具 | 自己イメージを形成するために必要な者 | 協力者、同僚・仲間 | 自己の変容に貢献する者 |
| 自己洞察 | 低 | 中 | 高 | とても高い |
| 価値観 | 弱肉強食 | コミュニティ | 自己決定 | 人間性・慈悲心 |
| 欲求 | 他者の欲求を退けること | 集団や組織に従属する | 自分独自の価値観を求める | 責任と限界を結びつけて自己を捉える |
| 支配欲求 | とても高い | 中 | 低 | とても低い |
| コミュニ ケーション | 一方向 | 1対1の交換 | 対話 | 真のコミュニケーション |
| 組織における 地位・役割 | 出世第一主義者 | 善き市民 | マネジャー | リーダー |
③書籍の構成と各章の要約
500ページに迫るボリュームの本書は、全十一章から構成されます。
以下、各章をコンパクトに要約していきます。
第一章:私たちはすでに成人以降の心の発達が何かを知っている
- 発達段階の理論的背景について述べています。
- ここでは人間の心の隠された領域として、目に見える行動や意思決定の背後で意味構築活動を行う心の深くにある目に見えない意識構造に焦点を当てて、それを心の成長と表現しています。
- この心の成長に「社会的・感情的発達」および「認知的発達」が該当します。
- また、それらは非連続な動きで成長するものであり、単に学習(能力開発)をして発達するものではないと指摘されています。
- コーチ・発達支援者はそうした目に見えない意識構造に踏み込む必要があり、その理論的なフレームワークとしてキーガンの発達段階モデルを理解することが有効と述べられています。
第二章:他者の話に耳を傾ける際に立てる仮説
- 発達論に基づいた傾聴・インタビュー方法について、「段階2:手段・道具的段階」を具体例に用いて述べています。
- 発達論に基づいた傾聴では、発話内容ではなく発話構造の理解に努める必要があります。
- 発話構造は簡単に特定できるものではないため、仮説を構築しながら、徐々に仮説を検証していく姿勢が必要になります。
- 例えば、発達段階2の特徴として「自己の欲求を満たすための手段・道具」として他者を捉えている点が挙げられます。
- クライアント(発話者)が「困ったときに同僚に助けてほしい」というテーマで語っていたとき、その重心は自己の欲求を満たすことにあれば、それが依存的な語りであったとしても発達段階3で想定される「依存」と同じ意味ではないことに注意する必要がある、と述べられています。
- 一方で、「この発話構造は段階2である」という仮説を立てた場合、段階3や4であるという可能性を軽視しがちになるため、常に反論を形成しながら丁寧に仮説を検証する姿勢が求められます。
第三章:クライアントの意識構造はどの発達段階にあるか?
- 段階2・3・4・5の特徴と、こららの間の移行期における課題について詳細に説明されています。
- 各段階を要約すると、「段階2:自分の単一的な視点しかとることができない」「段階3:物理的および内面化された他者の期待によって自分を定義している」「段階4:自分独自の歴史・価値観によって自己を定義している」「段階5:過去の成功や失敗、自分の歴史などを超越し、もはや自分の特定の側面と同一視することはなく、他者を導くことができる」となります。
- また、この章の重要なポイントとして、コーチ・支援者は、傾聴のスキル・能力よりもコーチ自身の発達度合いが重要であると指摘されています。
- 例えば、段階3のコーチは、クライアントから適切な距離を取ることができず、クライアントの発達構造の理解が不十分なまま効果的な支援を行うことができないため、コーチには段階4以上の成熟が求められると言えます。
第四章:「単なる」傾聴から仮説に基づいた傾聴への移行
- 発達論に基づいた傾聴の技術について、より詳しく述べています。
- 先述のとおり、発達論に基づく傾聴は仮説が重要であり、実証的な証拠を得るための意識的な仮説構築と検証が求められます。
- 一方、発達測定のインタビューでは、クライアントの立場に寄り添ってクライアントの意識の重心構造を理解する必要があり、クライアントの発達段階を探求するうえで、相手の話を公平に聴き入れる器のような存在として必要な情報を引き出していくことが求められます。
- そのインタビューの重要な四つのポイントは「クライアントの思考を決して妨げない」「コーチ自身の関心・解釈などを持ち込まない」「クライアントと同じ気持ちを感じることに躊躇しない」「インタビューでクライアントの発達段階を特定する情報を集められなければ、正しい分析結果を得られずに手遅れに終わる」と指摘されています。
第五章:発達リスクとポテンシャルの測定方法:移行段階の区別
- 主要な発達段階の移行段階の特徴について述べています。
- 発達段階を見ていくときには移行段階に着目し、意識の重心構造に加えて、退行リスクと現在の自己を超えていくポテンシャルを踏まえた範囲(レンジ)として捉えることが重要になります。
- 例えば、段階αと段階β(=α+1)の間には、α(β)、α/β、β/α、β(α)という四つの移行段階があり、その発達の過程で揺らぎながら葛藤や自己喪失を抱えることになります。
- このように移行段階を捉えていくと、段階2から段階5までの間に16個の発達段階を定義することができます。
- そして、クライアントへのフィードバックは、現状の発達段階の揺らぎを考慮しながら、次の段階に向かうための支援を意識することが求められます。
- そのため段階3と4の間にいるクライアントと、段階4と5の間にいるクライアントでは、フィードバックのやり方や方向性が根本的に大きく異なるという点に注意が必要です。
第六章:発達的葛藤をどのように理解するか?
- 移行期を含む16の発達段階が体系的に解説されています。
- この章は、移行段階の詳細な解説を提供していますので、読みごたえのある記述が多くあります。
- 移行段階のポイントをざっくりとまとめますと次のとおりです。
- 段階2から段階3の移行に当たっては「他者の視点の内面化」がキーワードで、自己の欲求・願望・自己イメージに関する自己開示を通じて、他者の期待や他者からの影響を把握することが重要です。
- 段階3から段階4の移行に当たっては「自己理論(自分独自の価値観)の構築」がキーワードで、内面化された他者と距離を取り、他者を尊重しながら、自分の個性・独自性を構築することが重要です。
- 段階4から段階5の移行に当たっては「自分の価値体系に囚われない新たな自己形成のプロセス」がキーワードで、自身を学習する組織とみなし、自分の限界を指摘してくれる信頼できる他者と深い関係性を結び、相互成長を志すことが重要です。
第七章:強力な会話の構造: 行間を読み取る聴き方
- 発達論に基づいたインタビュー技術について、事例を交えながら、より詳しく述べています。
- 発達測定インタビューには、「評価・測定メソッド」としての特徴と、「強力な会話を促す構造化されたインタビューとしての介入的手法」としての特徴を併せ持っています。
- 評価・測定メソッドとしては、クライアントの思考の流れに寄り添うことが最も重要であり、その後、発達理論に基づいた仮説・検証を行って、クライアントの思考の活性化を促進することが求められます。
- 強力な会話を促す介入的手法に関しては、クライアントをより高次の発達段階に導く問いかけの具体的事例および留意点について記載しています。
- ここでのポイントとして、コーチがクライアントよりも高度に発達していなければ発達支援は上手くいかず、自己流で発達測定インタビューの技術を習得することは危険であると指摘されています。
第八章:発達測定インタビューにおける仮説の検証方法
- 実際の発達段階の測定について、具体的事例を用いながら言及しています。
- インタビュー事例の分析に関して、大きく五つのステップで記述されています。
- ①インタビュー事例の全体に目を通して、クライアントの発達範囲に関する仮説を立てる。
- ②インタビューの細部を読み込んで、初期仮説に対して批判的な観点を持ちつつ仮説を強固にしていく。
- ③インタビュアー(コーチ)の強み・弱みについても検討しておく。
- ④分析シートを用いて、分析対象のビット(切片)ごとに評価し、仮説の検証を行う。
- ⑤分析結果を基に、次なる発達に向けてどのようにコーチング・メンタリングを行うかを検討する。
- 実際の分析シートの例などがあり、本章を通じて、インタビュー分析の実務的な理解を深めることができます。
第九章:発達論に基づいたコーチング
- この章では、コーチ自身を対象として、発達段階の視点からコーチングを捉えていく重要性について述べています。
- コーチングレベルとして、段階3の他者依存段階のコーチ、段階4の自己著述段階のコーチ、段階5の自己認識段階のコーチが想定されます(なお、段階2の道具主義的段階のコーチは、自分の欲求を満たすことに重心があるため、そもそも他者支援を行うコーチとしてふさわしくないと指摘されています)。
- 段階3のコーチは、他者の期待によって縛られているため盲目的にベストプラクティスを適用しがちで、必ずしも効果的な支援が期待できるとは限りません。
- 段階4のコーチは、自分独自のコーチングモデルを構築することができ、ややプロフェッショナルに近づきますが、自分のモデルに過度に固執してしまう懸念があります。
- 段階5のコーチは、自分の限界を相手にさらけ出し、クライアントとの相互発達を志向し始めて、「他者を支援する」という仮面を脱ぎ捨てた支援モデルを模索し始めます。
- ただし、コーチが高い発達段階(=段階5)にもかかわらず、対峙するクライアントの発達段階(=段階3)と間のギャップが大きすぎる場合、クライアントにとって負担がかかりすぎてしまい、実際の行動変容に結びつかない懸念も想定されると指摘されています。
- また、クライアントの発達段階よりもコーチの発達段階が低次の場合、むしろ発達的に有害・逆効果が生じる可能性があり、コーチ自身がプロフェッショナルになるためのメンタリングを受け続けて研鑽していく重要性が説かれています。
第十章:欲求/圧力分析
- 発達のもう一つの領域である「欲求/圧力分析」について、三つのケーススタディを用いて述べています。
- 欲求/圧力分析では、「自己の振る舞い」「職務に対する姿勢」「対人関係的側面(感情的知性)」の三つの側面に基づく18個の変数によってクライアントの行動的特性を分析します。
- 三つのケーススタディを通じて、クライアントの行動プロファイルを踏まえつつ、どのようにコーチング戦略を立てていくかが記述されていますので、詳しくは本書をお読みください。
第十一章:組織における発達的課題・問題
- ここまで個人の発達段階に焦点を当てていましたが、本章では組織への活用を想定して、組織力学および人材管理における発達論的課題について述べています。
- 組織におけるメンバーの発達プロファイルを見ながら、メンバー間の発達段階の均衡がとれているのか、マジョリティが低次の段階に偏っているのか(ピラミッド型)、高次の段階に偏っているのか(逆ピラミッド型)という観点から組織を類型化し、誰をキーパーソンとして組織への介入を検討するかに関する視座を与えてくれる内容が記載されています。
- また、職務の階層と発達段階が合致した組織を目指すことを理想としたとき、そのための組織のケイパビリティを測定・分析する視点も提供しています。
- ただし、本章は応用的な視点であり、今後の発展性を含めた指摘にとどまっているため、本書に記された内容だけで、組織への適用を十分に腹落ちさせるのは難しいように思います。
④本書で注目すべき5つのポイント
本書で注目すべき5つのポイントを挙げます。
- キーガンの理論モデルに関する段階2・3・4・5の特徴と各段階の限界、そして移行に関して、非常に解像度を高めることができます(詳しくは書籍を読んでくださいますと幸いです)。
この理論モデルを知っておくと、人間関係における意見の不一致の根源に関する共通言語を持つことができ、世の中に対する見え方が変わるとともに、自身の成長や相手の発達支援における道しるべを手にすることができると思います。 - コーチの傾聴姿勢について詳細に言及しており、特に支援者(インタビュアー)が行いがちな自身の好奇心や関心に基づく「なぜ」という質問形式は、発達論に基づくインタビューではあまり好ましくないという指摘は、個人的に大きな気づきとなりました(それによって、クライアントの現在の思考を妨げたり、思考の流れを断ち切ってしまう懸念があるとのことです)。
インタビュアーの解釈を基にして正解を提示するより、クライアント自身に探求させるというプロセス・コンサルテーションについて、あらためて考えさせられました。 - クライアントに適切な支援を行うには、少なくとも段階4が求められるという指摘が印象的でした(段階3ではクライアントに期待に応えようとしてしまい、過度にクライアントを喜ばせようとすることになるため、適切な支援ができないとされます)。
その意味では、コーチ・支援者側の発達段階の向上が重要であり、人に影響を与える立場にある人は、他者の発達を支援するよりも前に、むしろ自分の発達について向き合うことが重要と言えるかもしれません。 - クライアントの移行段階を見極めて、その移行段階に応じた支援・フィードバックが必要になります。
それを区別せずに、誰に対しても画一的なやり方をとってしまい、段階を考慮した対応ができないと、むしろクライアントを現状の発達段階にとどまることを強化させたり、あるいは後退させたりする危険性もあります。
このことは多くのマネージャーにとって重要な示唆となり、発達段階の違うメンバーには、その段階に応じた関わりを工夫しながら育成を行っていく必要があると言えます。 - 私たちは、つい人の発達(あるいは器)を評価・測定しようと思いがちですが、そもそも「評価する者」と「評価される者」という境界線をつくる発想が段階4にとどまっており、段階5では相互交流による相互成長を志向するようになり、自他の境界線がほぐれていくという指摘が重要と感じました。
そのような境涯に達しているコーチはレアだと思いますし、私自身も至らないところを日々振り返りながら、自分の成長を見つめ直し続ける必要があると考えました。
⑤本書を読む際の留意点としての5つのコメント
最後に、本書の留意点として、いくつかの批判的なコメントを付け加えておきたいと思います。
- 本書では高次の発達段階に進むときに低次の発達段階を超えて含むと表現されていますが、このときの“高低”の捉え方が過度な能力主義や優生学に結びつく懸念もあり注意が必要かと思いました。
さらに、段階理論(ステージモデル)はまるで退行がないような印象をもたらし、一度、段階5に到達・達成すれば、素晴らしく立派な人であるという固定的なラベリングを植え付けかねません。
本書では発達の範囲(レンジ)について言及をしていますが、実際は、置かれた状況や立場に応じて、本書で指摘されるよりもダイナミックに発達段階が動いている可能性があり、それは根本的に人格的な優劣や良し悪しを測るものではないという前提の認識を持っておくことが重要ではないかと思います。 - 本書では、インタビューデータを数値化して、発達のリスクとポテンシャルを評価しています。
たしかに、本書の評価手法は作り込まれていますが、正確な測定には少なくとも1年半以上のトレーニングが必要とされ、本書を読むだけでは使いこなすのに不十分です。
組織への適用もかなり応用的で曖昧な内容あり、人の発達という相手の人生や人格形成に大きな影響を与えるコーチや支援者の職業倫理上、本書を読んだだけの中途半端な理解のまま、実際の発達支援の実務に持ち込もうとすることは副作用を及ぼしかねず、あまり望ましくないのではないかと思われます。 - 本書では、1時間のインタビューで発達段階を測定するという方法を述べていますが、そのやり方が本当に正しいのかは疑問です。
客観性や公平性を保つために第三者によるインタビュー調査を想定しているのだと思いますが、その分、インタビュー時間に制約が生じ、またクライアントから豊かな語りを引き出すための関係構築に関する問題も生じる可能性があります。
例えば、組織のメンバーの発達を考えるときには、管理職である上司が長期間一緒に仕事をする中で見えてきた豊かな情報があり、それに基づく直観のほうが案外正しかったりもするのではないかと思いました。
そういう意味では、外部コーチによる第三者的な介入だけがソリューションではなく、現場の上司が本書で述べられている成人発達理論を学び、自分自身の段階を成長させ続けるとともに、それによってメンバーの発達段階を見極められるようになることは、現実的には重要と言えるのではないかと思いました。 - 本書で述べられているとおり、段階2・3・4・5は隠れた意識の構造に関わるものですので、これを単に知識としてインプットしただけで、当人の重心にある意識の構造が変わるものではありません。
例えば、世の中のマジョリティである段階3の人が、今回の書籍を熱心に学んで、ラスキーモデルをベストプラクティスとして信奉し、そのやり方をマスターした気になって、これが正しい発達測定のやり方であると広めていくようなことをするかもしれません。
しかし、それでは真の意味で人々の発達を促すことにはつながらず、少なくとも段階4に到達していないと、本書で取り上げられたモデルを盲目的に信じたまま、モデルとしての正当性を振りかざし続けるという短絡的な行為を招いてしまいます。
本書をどう読むか、本書を通じて何を得ようとするかは、読み手の発達段階に多分に影響を受けるため、常に自分自身のことを俯瞰的に見て、自分の発達段階を成長させようと思えるかどうかが非常に重要になると思います。 - 本書のタイトルが「人の器を測るとはどういうことか」ということもあり、過度に測定に対して注目が集まり、測定が目的化してしまいかねないことへの懸念があります。
もちろん測定を通じて段階を可視化することに一定の意味はありますが、測定ばかりに目を奪われるとクライアントの発達に向けた変容を支援するという重要な目的を忘れてしまいがちになるため、注意が必要かと思います。
そもそも完全な妥当性を求めて、精緻に測定できるようになることは、どこまで必要なのでしょうか?
もし、クライアントの発達支援が目的であるならば、過度な妥当性追求や再現性への信奉は本来の目的を見失うことにつながりかねません。
したがって、コーチや支援者はプロフェッショナルを目指しながらも、その測定にはバイアスや間違いが常につきまとっているという認識を持ち続け、そのうえでクライアントに対して精一杯にできることをやろうとして臨む姿勢を持つことが現実的な落としどころではないかと思いました。
まとめ
タイトルの「人の器を測るとはどういうことか」という問いに対する明確な回答は、本書では述べられていません。
「器」という言葉は、日本語で翻訳された際に当てられたものであり、私たち日本人が想定する「器」とラスキー博士の想定している4領域の発達モデルは完全に一致するものでありません。
日本語の「器」とラスキーモデルで提示された概念との間にどのような重なりがあり、どのように違うのかに関する詳細な検討は、今後、私たち「人としての器」研究チームに課せられた役目ではないかと思います。
また「測る」ということに関しても、本書では、とても精緻な測定手法が解説されていますが、誰にとっても手軽に客観性高く測れるものではないとも述べられています。
本書の主旨を汲み取ると、結局、測定の精度を高めるには、評価者であるコーチ自身が発達を志向し、成熟していくしかないように思います。
そのために、自身の段階を定期的に見直していくような内省(リフレクション)を行い、より段階の高い人たちとの関わりや対話を通じて、自分の発達段階を引き上げていくような機会を持つことが大切になります。
そして、不思議なことに、段階5に至ると、「測る」という強権的な関わりを手放して、相互に学ぶという姿勢を持つようになると考えられます。
この点が矛盾すると思われるかもしれませんが、本書の内容を十分に理解し、そのうえでキーガンのステージモデルもある種の幻想だとわかり、そもそも人の器は測ることもできないし、測れたとしても複雑な現実の一切れを見ているに過ぎないという限界が真に腑に落ちたとき、はじめて「人の器を測るとはどういうことか」という問いに対する回答が明確になるのではないかと思います。
長くなりましたが、多くの人にとって重要な示唆と問題を提起してくれる優れた書籍に違いありませんので、どうか手に取っていただき、わからないところは一緒に対話しながら理解を深めていければ、とても嬉しく思います。
『「人の器」を測るとはどういうことか』(JMAM)出版記念イベントのレポート
第1回 2024年4月4日(木)ゲスト:中土井僚氏 レポートはこちら
第2回 2024年4月19日(金)ゲスト:羽生琢哉氏 レポートはこちら